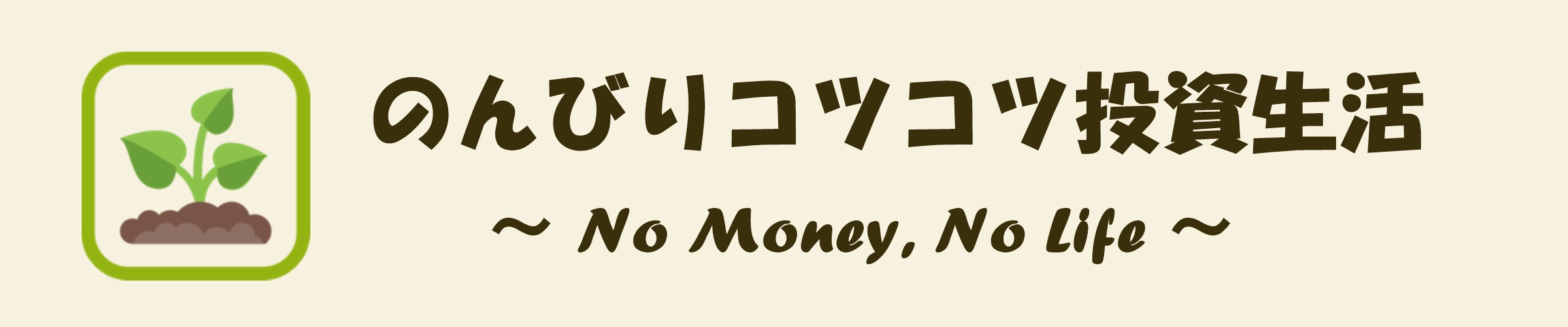しがらみゼロのFPブロガーMisaki(@fpmisaki2)です。
お金の不安が、全くないって方は、おそらくいないはず。
毎月、そんなにぜいたくをしているわけでもないのに、貯金ができないのはなぜだろう?
そんなお悩みを抱えてはいませんでしょうか。

貯蓄が足りないよぉ・・・宝くじ買わなきゃ!

それより、普段のお金の流れを見直して、上手に貯蓄ができるルールを作っちゃう方が確実だよ。
お金が貯まらないなぁ・・・って悩んでいる場合にありがちなのが、実は何にお金を使っているのか、しっかり把握できていないパターン。
もし、ちゃんと把握できている場合、そこには改善策のヒントが詰まっています。
家計費の支出を見直すというステップに進んじゃいましょう!
ですが、怪しいです・・・っていう場合、まずは自分のお金の流れを知ることから始めましょう。
特に近年は、共働きでおさいふが2つのご家庭が増えてきていますよね。
家計全体で、トータルで何にどれだけ使っているか、どれくらい貯蓄があるのか、実は分かっていないというパターン、けっこう多いんです 😥
お互いに、相方が貯めてるよね~と油断していて、いざとなったら貯蓄がゼロで大慌て・・・というのは、ありがちな話なんですよ。
むずかしく考えすぎる必要はありません。
自分に合った形で、家計簿をつけるところから始めましょう!
スポンサーリンク
「がんばりすぎない家計管理」は、なぜ大事なの?
当たり前の話ですが、収入>支出にならなければ、貯蓄をすることはできませんよね。
たとえ、年収が1,000万円あったって、よく考えずに1,000万円使っていたら、全く貯まりません 😥
私は、仕事がら、会社の財務状況を把握して改善策を考えたりしています。
会社でも家計でもそうなんですけど、収入を増やすのって、そんなに簡単なことじゃない💦
なので、まずは支出のクセを洗い出していくことから始めます。
お金の流れをよく見ていると、
- これってホントに必要?
- 別の方法にした方が安くない?
というものが、必ず浮かび上がってくるんです。
浮かび上がってきたものを、1つずつつぶしていくと、余裕資金が生まれます。
余裕資金があれば、時間を味方につけて、お金に働いてもらうことができるようになります。
いわゆる、リスク資産と呼ばれるものの活用です。
リスク資産を上手に活用すれば、貯蓄をさらに増やすことが可能です。
この順番は、とっても大事。
いきなり、株などのリスク資産でもうけてやろう! と考えてしまうと、投資がギャンブルになってしまいます。
めんどくさいなぁと思うかもしれませんが、
まずは、日常のお金の流れをしっかり把握することが、良い循環を生み出すための第1歩。
ただ、苦しかったり、めんどくさすぎても続きません。だって、人間だもの 😉
苦しくなったり、イヤになったりする感覚は、本当に人それぞれ。
私にとって心地よい方法が、あなたにとっては苦痛かもしれません。
人は人、自分は自分。
「ゆるーく、がんばりすぎない」をテーマにすえて、家計簿の作り方を考えてみましょうね。
がんばりすぎない、家計簿の作り方。「自分のテンションが落ちないかどうか」をベースに考えよう。
まずはじめに忘れてはいけないこと。
家計の状況を把握すること、要は、収入や支出の状況を見える化することが、家計簿の目的です。
家計簿がイヤになっちゃう多くのパターンは、「家計簿をつけること」が目的になって、形を整えるのがめんどうになっていく・・・というものです。
細かくあわせようとするよりも、まずは、ざっくりイメージがつかめればOK!
そんなふうに、自分の気持ちを軽くしたうえで、家計簿に向き合っていきます。
日記をつけたり、手帳をつけるのが好きなら、徹底的に自分好みにアレンジ
私もそうだったんですけど、手帳に色とりどりのペンで書きこんだり、シールを貼ったりしながら管理をするのって、テンション上がりませんか?
もし、当てはまるなぁと思ったら、手書きの家計簿にして、思いっきり自分好みにアレンジ。
義務としての家計簿ではなく、作品をつくる感覚で楽しんでみるのも1つです。
使いやすくておすすめの家計簿を、いくつかピックアップしてみますね。
高橋書店 プチ家計簿
![]() 手帳メーカーが作っていますので、家計簿っぽくないデザインですし、シンプルで書きやすい。
手帳メーカーが作っていますので、家計簿っぽくないデザインですし、シンプルで書きやすい。
手帳感覚で使いたい方には、おすすめです。
ダイゴー ギンガムチェック家計簿
とにかく自由度が高いので、カスタマイズ派には使いやすいです。
そして、クレジットカードの利用記録がつけられるのも大きな特徴。
意外と多くの家計簿にはクレジットカード用の項目がなかったりします。
レシート貼るだけ!簡単家計簿
こちらは、最初からかわいらしい見た目になっています。
その名の通り、レシートを貼って家計簿を作るので、細かい転記がいらないのでラクです。
我が家の夢や目標プランが書けるので、くじけそうになったら見返すことで、テンションアップ!
こんな感じで、使いやすい家計簿をアレンジしていくのもいいですし、大学ノートやルーズリーフで自作しちゃうのも1つの方法です。
薄い方眼タイプのノートは、自由なアレンジには使いやすいですよ。
完全オリジナルだと、さらに愛着がわきますね 😉
パソコンの利用に慣れているなら、Excelで計算ラクラク
お仕事などで、Excelを使い慣れているという方や、Excelを使いこなせるようになりたいなぁと思っている方は、Excel家計簿がおススメです。
グラフ化してみたり、自分好みのアレンジもしやすいですね。
Excelが得意な方は、完全自作でもいいですが、無料で公開されている家計簿用のテンプレートを活用するのが手っ取り早いです。
これ以外にも、自作のExcel家計簿を公開しているサイトがいくつもあります。
「Excel 家計簿」で検索してみると、いろいろと見つかりますよ。
パソコンは使わないけど、手書きはめんどう。それなら、スマホアプリを使ってみよう。
パソコンをいちいち起動するのはめんどくさいし、気が向いたときに、ちょこちょこつけるのがあっているという場合、スマホの家計簿アプリが使えます。
無料で使えるものを、いくつかご紹介しますね。
- レシートを読み取るタイプの「レシーピ」は、レシートの読み取り精度が比較的高いです。
- 自分で打ち込むタイプの「おカネレコ」は、金額の情報と一緒に、写真も登録することが可能です。
- とにかくシンプルで入力しやすい「シンプル家計簿-Moneybook」は、余計な機能がないので、気軽に使いたい方にはいいでしょう。
とにかく手間をかけたくないなら、総合管理タイプの家計簿アプリが最強
有料サービスになる場合もありますが、総合管理タイプの家計簿アプリを使ってみましょう。
銀行口座、クレジットカード、電子マネーなどを登録しておけば、勝手に費目分けをしてくれる、優れものです。
支払いをクレジットカードや電子マネーに集約していれば、しばらく使い込んで費目振り分けを覚えさせれば、ほぼ自動化するなど、大変心強いツールです。
忙しいし、他の部分に時間を使いたいという場合には、有料だったとしても、それ以上の価値はありますね。
- マネーフォワード-連携先の口座が豊富。株式やFXの資産管理まで可能です。
- Zaim-銀行やクレジットカードの明細を自動取得して分析してくれます。
- Moneytree-レシート読み取り型ではありませんが、取引明細をAIが自動判別して振り分けてくれます。
私個人的には、Excelに慣れていることと、自分のお金の情報をアプリに集約してしまうことに対する不安感もあり、まだ実際には使っていません。
ですが、今の技術の進歩や世の中の流れを見ている限り、お金に限らず個人情報は集約化されて、いざとなったら丸見えの状態になっていくのだろうなと感じています。
どうせ情報が集約されていくのであれば、隠しておいても仕方がないと割り切って、便利さを追求していくのもひとつですね。
こんな感じで、自分にあっていそうな方法で、家計簿をつけてみてください。
しつこいようですが、家計簿をつける目的は、収入と支出の大まかな流れをつかむこと。
1円単位で、数字が合わない! と悩んでいたら、すぐに嫌になります。
私は、経理事務をしているという仕事柄、あんまり数字が合わなさすぎると逆にストレスになるので、Excelで自分用の家計簿シートを作って管理しています。
レシートを見ながら入力しますが、支払い月はクレジットカードの引き落とし時期にあわせて振り分けていき、口座残高と家計簿の増減が、だいたい一致するようにしています。
クレカのレシートとWeb明細をチェックして、入力したらシュレッダー。
こうすることで、ついでに
- 変な請求が混ざっていないか?
- 今月の請求額が高額にならないか?
のチェックもしちゃってます。
そのかわり、現金の部分はざっくり管理です。
(そもそも、極力カードや電子マネーを使いますので現金支出が少ないのですが・・・)
なるべくレシートをもらうようにして、入力していますが、レシートがない支出(自販機とかお賽銭とか)は、覚えていたら入力するくらいのゆるさにしています。
ちなみに、交通費は細かく把握していません。
PASUMOのオートチャージ機能を使って、チャージした金額=交通費として入力しちゃっています。
家計簿の費目分けはシンプルに。後からアレンジすればOK!
手書きの場合やExcelで作る場合には、まずはシンプルな費目分けではじめてみましょう。
とりあえず、あると便利な支出費目としては、
A.支出の見直しがしやすいので、ぜひ把握しておきたい項目
- 貯蓄
- 住居費
- 光熱水費
- 通信費
- 保険料
B.状況に応じて、分けておくと便利な項目
- 食費
- 日用品・雑貨費
- 衣服費
- 美容・衛生費
- 趣味・娯楽費
- 交通費
- 教育費
- 医療費
- 交際費
- 小遣い
- その他
Bの費目は、たくさんありますが、お好みにあわせてチョイスすれば大丈夫です。
細かく分けるのが面倒な場合は、
- 食費
- 日用雑貨費
- 娯楽費
- その他の特別費
ぐらいでも構いません。
家計の費目は、それぞれのご家庭で特徴が違います。
統一された費目にこだわらず、感覚的に分けやすい方法にしておくことが大事です。
その方が、結果として使いやすいものに育っていきます。
続けていく中で、見えてくる部分もありますので、費目のアレンジができるような家計簿フォームを選んでおきましょう。
ところで、支出のトップに「貯蓄」があげられていますね。
貯蓄は自分のお金なんだから、支出じゃないんじゃないの???
そう思われた方もいるかもしれません。
でも、貯蓄するということは、「普段使えるお金から切り離す」ことになります。
なので、普段使いのおさいふから出ていく=支出として扱うのです。
家計管理の最重要課題。それは、先取り貯蓄のルール化です!
支出の費目分けリストのトップに貯蓄が上がっているのは、大きな理由があります。
それは、先取り貯蓄をして欲しいから!
毎月あまった分を貯蓄すればいいや。
こう考えていると、なかなか貯蓄はできないものです。
誰だって、お金があると思うと使ってしまいますからね 😉
目標は収入の10%~20%。
ちなみに、基本は月々3万円、ボーナス月(年2回)は10万円を貯蓄すると、年間50万円が貯められる計算です。
もちろん、無理しすぎもいけませんので、状況に応じて月1万円からはじめてもいいでしょう。
家計の状況を把握 → 支出の見直しをする → 先取り貯蓄額をup
こんな流れがベストです。
銀行の自動積立定期預金、会社の財形貯蓄など、指定した日や給与天引きで自動的に振り替えられる制度がありますので、なるべく早めに設定をしてしまいましょう。
ちなみに、iDeCoは究極の先取り貯蓄です。
節税効果が抜群なので、やってみたくなりますよね。
ですが、60歳までは絶対に引き出すことができませんので、ある程度の生活防衛資金が貯まってから、はじめた方がいいですよ。
もし、手元の貯蓄が少ないのなら、まずは定期預金や財形貯蓄から。これは絶対お忘れなく!
おわりにー家計管理の第一歩は、お金の流れを知ること。
何も考えずにお金を使っていたら、どんなに収入が増えたとしても、浪費をするだけです。
本当の意味で豊かな人は、お金と上手に付き合って、お金とともだちになっています。
困ったら、FPとか専門家に相談すればいいじゃん! と思うかもしれませんが・・・
例えば、医者に行った時には、頭が痛いとか、おなかがシクシク痛いとか、自分の症状を伝えることで、適切な診察が受けられますよね。
お金の問題も同じです。
現状が伝わらなければ、お金のプロであっても、あなたにあった改善策を提示することはできません。
一般論をお伝えする程度にとどまってしまうでしょう。
まずは、
- お金の流れをつかむ
- 少しでもいいから、先取り貯蓄をはじめる
ここから家計管理の旅が始まります 😉
さぁ、次は支出の見直し。誰でも当てはまりやすい、固定費の見直しについて考えてみましょう。
スポンサーリンク
スポンサーリンク